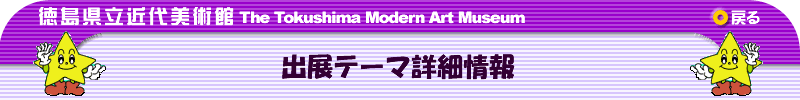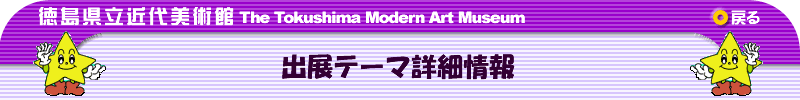| 説明 |
まず油彩画ですが、徳島県ゆかりの作家でもある伊原宇三郎、山下菊二、高井貞二、等の作品をご覧いただきます。
伊原は1925年から1929年にかけて焼く4年間渡仏しますが、〈座れる裸婦〉〈海辺の裸婦〉はともに渡仏した年に制作されたものであり、当時の伊原の勉強ぶりがうかがえます。山下、高井の作品は、晩年のものですがともに代表的な作風をよく表しています。一方猪熊、瑛九、元永等の作品は、初期に当たるもので画風の確立を目指し色々な試みを展開しています。
次に日本画では、徳島ゆかりの作家としては廣島晃甫と市原義之があげられます。廣島は大正時代から日本画に洋画の技法を取り入れるなど、村上華岳等国画創作協会のメンバーらとともに、日本画の改革を積極的に推し進めた作家の一人として高い評価をうけています。戦後日本画は、「日本画滅亡論」などが唱えられ激動の時代を迎えますが、片岡球子〈浮世絵師安藤広重〉、中村正義〈男女〉、小嶋悠司〈穢土〉等の作品は、日本画の新しい方向を指し示すものといえます。
最後に彫刻では、植木茂、建畠覚造、浜田知明、福岡道雄等を 展示いたします。植木は主として木を素材とした作品を多く制作していますが、〈トルソ〉は晩年の大作の一つとして貴重な作品と言えます。建畠の〈Waving Figure-29〉は、人のかたちを抽象的に表現した作品としてユニークな存在です。一方浜田、福岡の作品はともにブラックユーモア的なものですが、浜田は政治や社会の矛盾、疎外感、社会問題などをアイロニーたっぷりに表現しています。福岡は、河原や池などをモチーフとした風景彫刻の作家として注目されていますが、自然と人との関わりを主要なテーマとしています。 |