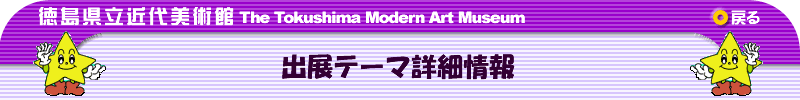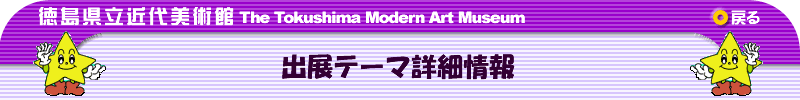| 説明 |
今回は、99年度の新収蔵作品を中心にご紹介します。なお、前期(6月4日まで)と後期(6月6日から)で一部展示替えを行います
・20世紀の人間像−新収蔵の日本画
このコーナーでは、前期(4月29日-6月4日)に、橋本関雪の<五柳先生>と尾形月耕の〈花見うららか〉を紹介します。五柳先生とは中国の詩人陶淵明のことです。明治末期から大正期にかけて、関雪は中国や日本の歴史や文学から題材をとった人物表現を軸に制作を行っていました。また、月耕は浮世絵系の作風をもとに江戸の市井の生活を近代的に描こうとした作家です。
後期(6月6日-7月16日)には鏑木清方の<夏姿>、冨田渓仙の〈南泉斬猫〉などの作品を紹介しま
す。清方は、江戸文化の教養に支えられた粋の美意識を反映した人物画を描いた作家です。その中
でも数多くの優れた美人画を残しました。
渓仙の作品は、一匹の猫を二人の僧が取り合うのを見て、僧南泉普願がそれを取り上げ両断したと
いう説話に基づくものです。
・20世紀の人間像
今回は、新収蔵作品2点を含む3点の藤松博の作品を紹介します。彼の初期の作品である<手相(白い手相)>と60年代の2点とでは作風が大きく変わっていることに気づきます。彼は基本的に人間をテーマに展開を見せるのですが、今回見られるのは、彼の最初の大きな変化です。
鈴木治は陶による新しい表現を開拓している作家です。<ある彫刻家の肖像>とは、彼と親交の深かった辻晋堂の肖像です。
奈良美智ののタイトルの意味は、<小さな巡礼者(夜うろつく人)>ということです。巡礼者が聖の存在である一方、夜うろつく人とは泥棒や売春婦を意味する邪悪な存在です。奈良は子供とはどちらにもなりうる存在だと見ているのです。 |