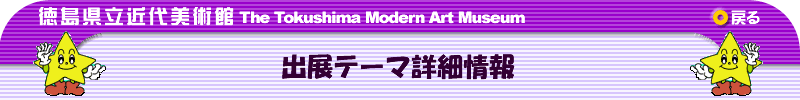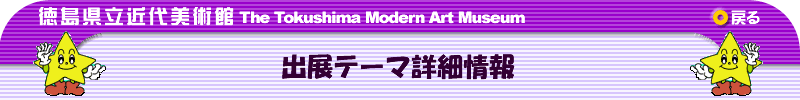| 説明 |
20世紀、美術の世界では様々な表現が生まれました。それは、作家たちが「何を表現するか」ということにもまして「どのように表現するか」ということを重要視するようになったからです。その結果、一見したところ難解な作品が数多くなりました。そこで、当館では、取っかかりとして人間像を選びました。すなわち、どのように表現されていようとも、ここで展示されている作品には、人間像という拠りどころがあるのです。どんなに取っ付き難くく思えても、まず、そこに人の姿を見つけ、なぜこのような姿に作られたのか、思いをめぐらせて下さい。作家自身が登場する美術作品として、まず思い浮かぶのは自画像でしょう。しかし、作品名から、あるいは作品を一見したところではよくわからないものの、作家が何らかの形で登場している作品は珍しくありません。今回は、そのような作品をまとめて展示します。ここではその中の何点かを紹介します。
大久保英治の<影シリーズ>5点は1998年1月に当館で開催された「大久保英治 四国の天と地の間 阿波の国より歩く」に出品されたものです。この展覧会では四国八十八ヶ所の遍路道を軸に四国各地を歩きながら制作された作品やその過程で拾得した素材を用いて制作された作品が展示されました。<影シリーズ>は季節を通して制作されたものです。作家大久保英治の影にそれぞれの場所の石や花々を重ね合わせることで、作家自身とその時その場の自然とが関わったことを記したのです。
植松奎二の作品が撮影されたのは、京都市美術館のある展示室の入口です。これらの作品はその直後に同じ美術館で開催された展覧会の出品作でした。写真に登場しているのは若き日の植松自身。「水平」、「垂直」、「直角」という概念を目に見えるようにしようとした試みなのです。しかも、他者の行為を見るのではなく、自らが体感することも重要だったのです。
宮崎豊治の<眼下の庭>は、宮崎の生家やそのまわりの土地の記憶を原型としています。そして、作品に登場する小さな人型は祖父母や両親、兄、幼い頃の自分を含めた家族関係の投影であると作家は語っています。その他、このテーマで石原友明、福岡道雄の作品なども展示しています。 |