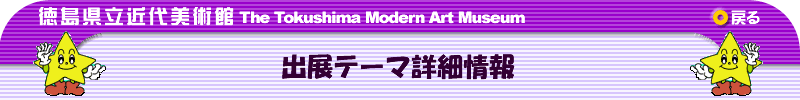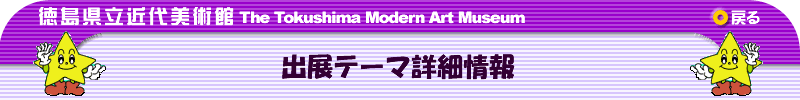| 説明 |
1926年、清原は第7回帝展に浴衣姿の自画像を描いた「夏の男」を出品した。色彩を抑制して、褐色の背景から浮かび上がる浴衣の白が印象的な作品となっている。この作品はこの時期の清原の画風の発端となった。
この後帝展に出品した1928年の「夏の女」、29年の「小憩」、30年の「南の椽」では、人物を画面に大きく描き出し、褐色と白の鮮やかな対比を見せていて、これらが「夏の男」につながる表現であることが理解できる。しかし同時に筆使いは流麗さを増し、関心が西洋的な立体感の表出よりも、次第に筆さばきの妙味へと向かっていったことも理解できる。
当時の展覧会評を見ると、当初はこれらの作品は比較的好意的にあつかわれている。しかしフランスから次々と帰国してくる留学生たちの新しい表現が帝展でも注目を集めるようになると、次第に顧みられなくなっていった観がある。
こういった作品とともに、多くの静物画も残している。現存する中で比較的早い時期の制作と考えられるのが「緑の皿のある静物」である。ここでは生真面目な描写ぶりを見せているが、やがて筆触を生かして「洋梨と野菊」のように、落ち着いた色彩の中にも華やかさを持った世界を描くようになる。
この時期出品した展覧会としては、帝展のほかに聖徳太子奉賛展、光風会展、中央美術展などが知られている。特に光風会へは前の時代から熱心に出品を続け、1928年に会友、1931年に会員となった。 |