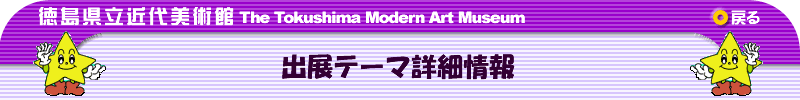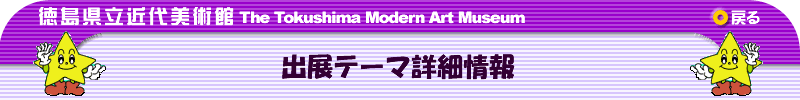| 説明 |
1908(明治41)年に帰国した荻原は、その年の第2回文部省美術展覧会(以下文展と省略)に出品、三等賞を得て日本の彫塑界にデビューします。朝倉も同展に出品、二等賞(一等賞は授与しないこととなっていたので事実上の最優秀賞)となり、華々しく登場します。第3回文展にもそれぞれ出品しますが、荻原の〈北条虎吉像〉(三等賞)と朝倉の〈吊された猫〉とが、高村光太郎により対照的に批評されます。高村は作品に「生」があるかどうかを作品の判断の拠り所として荻原を称賛し、朝倉を難じます。確かに〈北条虎吉像〉は内部にその人の生命をたたえながら手堅くまとめられた肖像彫刻の逸品といえるでしょう。しかしながら〈吊された猫〉にしても、高村は「彫刻を彫刻として扱ったところに愉快なところがある」と一定の評価を与えた上での批評であり、当時の、観念を造形化しただけの作品が大手をふるっていた中では、猫の形態を自然に捉えた本来的な作品であるといえます。1910(明治43)年4月20日、荻原は30歳の生涯を閉じます。この年の第4回文展には絶作〈女〉が遺作出品され三等賞となります。〈女〉は日本近代彫塑中、生命を造形化した名品として知られている作品です。朝倉は〈墓守〉(二等賞)他を出品します。この〈墓守〉は、朝倉が観念的な制作から自然を主眼とした制作に意識的に転換した、その後の出発点となる作品です。朝倉にとっての自然とは、観る者に違和感を感じさせない「らしさ」を備えた外形的な形態として捉えることができます。荻原の〈女〉と朝倉の〈墓守〉を比べてみると、内部(生命)の〈女〉も、外部(形態)の〈墓守〉も、その立つ地平に開きがあるものの、いずれも彫塑作品として自立しています。日本近代彫塑の一つの到達点がここにあります。 |