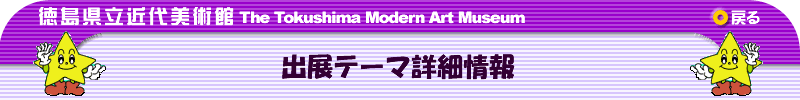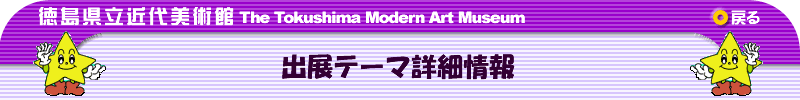| 説明 |
伊上凡骨(いがみ ぼんこつ) 1875(明治8)〜1933(昭和8)年
明治から昭和初頭にかけて活躍した木版画の版木彫り師です。現在の徳島市中常三島町に生まれました。本名は純藏。雅号の「凡骨」とは「平凡な器量の者」という意味で、歌人の与謝野鉄幹が命名したと伝えられています。
徳島で高等小学校を卒業したあと、17歳の年に上京して浮世絵の版木彫り師、二代目大倉半兵衛に師事しました。大倉のもとで伝統的な技術を学び、早くから浮世絵版木の天才的な彫り師と知られましたが、やがて洋画を木版で再現することに専念します。水彩やパステル、鉛筆などの複雑な筆触や色彩を見事に再現し、特に軟らかい鉛筆の線のかすれを再現した「サビ彫り」は「神技」とうたわれました。
まだ写真製版が印刷技術として確立されていなかった時代です。伊上が彫る版木は、多くの文学者や美術家の絶大な支持を集め、当時の本や雑誌の表紙絵や挿絵を数多く手がけることになりました。与謝野寛、晶子夫妻や武者小路実篤らの文学者や、岸田劉生、石井柏亭、平福百穂、冨田渓仙、速水御舟らの画家に敬愛され、特に夏目漱石は、自著の装丁は凡骨でなければならないと指名していたといいます。この時代の日本の出版界を、裏で支えた木版の版木彫り師でした。 |