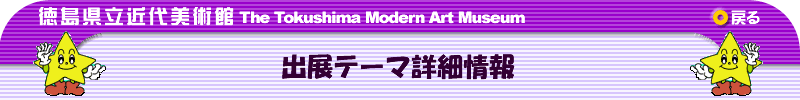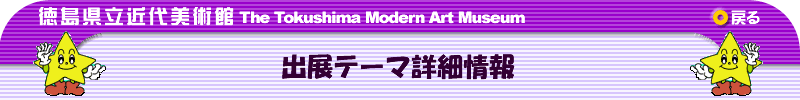| 説明 |
戦後になると、表現媒体としての挿絵本は、画家たちや画商、出版者の間で認知され、制作のノウハウも蓄積されていきます。印刷技術や用紙、インクなど、制作を取り巻く物理的な環境もよくなり、それに伴って表現の幅も広がっていきました。そして、少し手を伸ばせば手が届く美術作品として、一般大衆のコレクターによる顧客層も形成されていきます。
シャガールが何年もかけて練り上げた美しいリトグラフの挿絵がついた、古代ギリシャの詩人ロンゴスの物語〈ダフニスとクロエ〉。マティスが切り紙で作った作品をステンシルで刷り、自らの文章を添えた〈ジャズ〉。早熟の天才詩人ジャン・コクトーが、自らの挿絵と文章によって生涯にたった一つ作った童話〈おかしな家族〉。
日本でも、同様の出版が行われるようになります。シュルレアリスムの源泉となった謎の詩人ロートレアモンの詩に、戦後日本を代表する銅版画家駒井哲郎が挿絵を付けた〈マルドロオルの唄〉や、詩人であり、戦前から戦後にかけて美術評論の分野でも大きな足跡を残した瀧口修造の詩にミロが挿絵をつけた〈ミロの星とともに〉。また、デビュー間もない池田満寿夫は、〈屋根裏の散歩者〉を初めとする豆本を多数制作しました。
戦後、挿絵本の制作は、戦前以上に活発化し、多様化していきますが、豪華版や限定版が横行する状況への反発も生まれ、やがて一九六〇年代以降にアーティスツ・ブックスが発生する背景の一つともなっていきます。 |