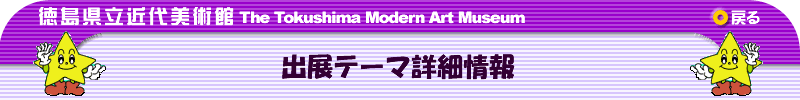
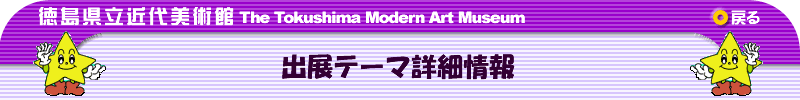 |
|
| 「ランド・アートをめぐって 1982年頃〜2000年代」の詳細情報 | |
| ●くわしい検索へ ●美術館トップへ | |
| テーマ名称 | ランド・アートをめぐって 1982年頃〜2000年代 |
| 期間 | 2024年7月13日(土)~2024年9月23日(月) |
| 展覧会名称 |
大久保英治:辺境の作家1973-2024 |
| 説明 | 大久保は1981年に教師を辞めて美術家に専念します。この頃から海岸を歩き、流木や葉、羽、石などを使った自然を要素とする制作へと向かいます。そして、このような制作がランド・アートと呼ばれていることを知るようになりました。 当時、大久保は次のような言葉を残しています。 「環流:物が生まれ、土に還っていく自然の流れの中で、物と物をある時点で結びつける。−それはあたかも流れをスロービデオで見、ストップさせたかのようである。その状態を私は作品として提示しようとしている。古代人への想いをこめて、自然の物、身の回りにある物のもっている力強さを、ごく当たり前の形で表出することに私は心を配っている。*」 これは大久保のランド・アートにとって重要な考え方となります。そして、1990年代以降ランド・アーティストとして、世界からも注目を浴びるようになりました。また、「四国八十八カ所」(1998-99年)をはじめとして各地を精力的に歩き、「歩行」が大久保のトレードマークの一つとなりました。 現地の材料で制作した屋外作品の多くは既に消滅していますが、本展では、新聞紙で作った紙粘土と流木で構成し、黒く塗り込めたオブジェ(〈波〉、〈水滴〉)や、自然にできた影で時間を見せる〈影シリーズ〉、海岸に漂着した大量の使い捨てライターの集積に時間や場所、出来事などを見る〈水の記憶〉などを展示します。 自然や大地と関わる作品は、自然保護や環境問題がテーマであると見なされることもよくあります。しかし大久保の場合は、「点、線、面」、「垂直、水平」、「時間」、「場所」という初期から共通する根源的な問題意識の追及が制作の基盤となっています。 *大久保英治 『A WALKING MAN-OKUBO』児玉画廊 1990年 pp.1-2 |