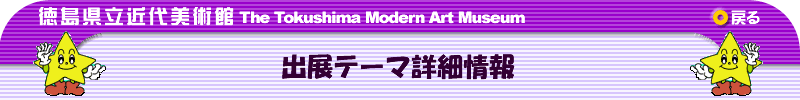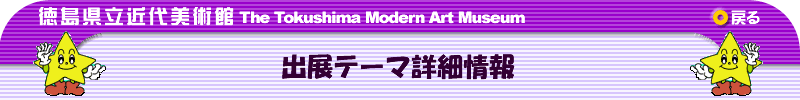| 説明 |
流派の表現が交差し、重なり合ってくる明治20年代は、帝国憲法が発布され、日清戦争が勃発するなど、正負入り交じりながら近代国家としての日本が形成されようとしていた時期でした。中国からの影響を排除し、日本独自の表現が求められた時期でもありました。日本の歴史を題材にした歴史画が大和絵の表現に学びながら制作されたり、久保田米僊〈海陸戦斗図〉(No.77)のように、日清戦争を取材した戦争画が生まれたのも、同じような社会的背景によるものといえるでしょう。またそれは、この時期に、「日本画」という言葉とともに、新しい「日本画」の表現が生まれようとする背景でもありました。
鈴木松年〈八岐の大蛇退治〉(No.71)は、日本神話から、小堀鞆音〈那須宗隆射扇図〉(No.72)や川辺御楯〈新田越後守義顕決戦之図〉(No.74)などは、日本の歴史から題材をとっています。この時期の歴史画制作の流れは、江戸時代において、歴史画や人物表現を得意としなかった流派や画家を含む画壇全体をつつみこむ勢いがあり、竹内栖鳳も、歴史画とは無縁な表現を続けていたものの、この頃、源平の戦いを題材とした作品(No.78)を描いています。このような歴史画制作は、各流派の表現の交流と交差をさらに推し進める要素もあったのです。 |