美術科教育学会2008年度 第4回西地区研究会報告
テーマ: 創造を生涯の友にする「鑑賞遊び」
日時: 2008年11月15日[土] 13:30-16:40
会場: 徳島県立近代美術館(講座室)
主催: 美術科教育学会西地区会、徳島県立近代美術館
後援: 徳島県小学校教育研究会図画工作部会、徳島県中学校教育研究会美術部会
参加者: 49名
→開催概要のページ →美術科教育学会通信No.70
※このサイトの本文は、『美術科教育学会通信No.70』からの転載です。
1 概要
研究発表 13:30-14:45
Ⅰ「パスポート力を涵養する鑑賞遊び」
濱口由美(徳島市富田小学校)
Ⅱ「鑑賞パスポートを手にした子どもたち」
濱口由美・竹内利夫(徳島県立近代美術館)
パネルディスカッション 14:55-17:00
「鑑賞遊び」の習得・活用・探求-図工室から生涯美術へ-
パネリスト:赤木里香子(岡山大学教育学部)/森芳功(徳島県立近代美術館)/山木朝彦(鳴門教育大学)/山田芳明(鳴門教育大学)/結城栄子(徳島県立総合教育センター)五十音順
司会:濱口由美/竹内利夫
2 研究発表・鑑賞シート授業研究会
「創造を生涯の友にする『鑑賞遊び』」とのテーマを掲げ、新しい教育課程における学習指導の具現的な方法論として、生涯の鑑賞パスポート力を涵養していく「鑑賞遊び」について考察した実践研究の発表を行った。また、たくさんの方が、鑑賞遊びの様々な実践を知ることで検証的視野から研究会討議に参加できるようにと願い「第5回鑑賞シート授業研究会」も同日開催した。
(1)研究発表I・II
 今回の研究発表では、改訂学習指導要領の基本方針でもある「習得・活用・探求」の学習指導の視点から、これまでの美術作品を対象とした鑑賞遊びにかかわる実践活動を捉え直すことで、「鑑賞遊び」が新しい教育課程における具現的な鑑賞プログラムとして様々な可能性を持つことを示した。また、生涯美術への素地を育む鑑賞活動としての「鑑賞遊び」のスタンスを表明することで、2部のパネルディスカッションへの問題提起とした。
今回の研究発表では、改訂学習指導要領の基本方針でもある「習得・活用・探求」の学習指導の視点から、これまでの美術作品を対象とした鑑賞遊びにかかわる実践活動を捉え直すことで、「鑑賞遊び」が新しい教育課程における具現的な鑑賞プログラムとして様々な可能性を持つことを示した。また、生涯美術への素地を育む鑑賞活動としての「鑑賞遊び」のスタンスを表明することで、2部のパネルディスカッションへの問題提起とした。
研究発表Iは、鑑賞遊び「音のかくれんぼ」を軸とした授業記録を基に、「習得」から「活用」へと連動していく過程での子どもたちの変容を分析しながら活動の様子を報告した。そして、鑑賞遊びのルールの習得が、自立的な活動へと展開していくための「作品や友達とかかわる力」となることを検証した。また、このルールを伴う鑑賞遊びの学習スタイルが、一人一人の確かな居場所と互いを認め合う相互鑑賞の場をつくりだす要因であることも多学年にわたる事例研究を基に報告した。
研究発表IIでは、美術館での「クレーの絵本朗読会」や「夏休み親子シーがる・た大会」、地域の文化財を会場とした来場者参加の「富田の町でシーがる・た」展など、鑑賞遊びを活用することで探求的な活動の場が生まれた二つの合科的単元学習の実践を報告した。美術館を舞台とした鑑賞遊びの活動は、様々な人との交流を生み出し、色や形などによるコミュニケーションを通して社会とかかわろうとする態度を育む。そして、鑑賞遊びの活動を,学校生活・美術館・地域社会の中で活用していくことで、個々の探求的な活動がひろがり、生涯鑑賞パスポート力の確かな素地が一人一人に培われてくるものであるとまとめた。また、竹内学芸員からは学校教育の支援活動として活用した美術館での取り組みが報告され、社会教育の場における「鑑賞遊び」の汎用性や有用性が子どもたちの活動の足跡から示された。
(2)第5回鑑賞シート授業研究会
鑑賞シートを活用した実践開発とそのネットワーク確立のために集まった塾生(ほとんどが小学校教員)による、自主的な研究会を平成18年から続けている。今回は、鑑賞シートNo.7「吹田文明の色と光」の実践報告である。
 1時間目は、脇本正久教諭の5年生児童による「音のかくれんぼ」の実践報告。子どもたちの評価活動を鑑賞遊びの活動に組み込むことで、相互鑑賞の場がより意欲的な活動となることや批評的な見方も高まることを提言された。
1時間目は、脇本正久教諭の5年生児童による「音のかくれんぼ」の実践報告。子どもたちの評価活動を鑑賞遊びの活動に組み込むことで、相互鑑賞の場がより意欲的な活動となることや批評的な見方も高まることを提言された。
2時間目は、それぞれの学校で実践された「音のかくれんぼ」の輪番制フリートーク。鑑賞遊び「音のかくれんぼ」を軸にしながらも、対象学年や学校の取り組みに合わせた個性的・創造的なシート活用実践が報告された。国語科の学習と合科的に展開した実践や美術館のWeb番組を活用した指導者たちは、「言語活動の充実」や「放送・視聴覚教育」といったそれぞれの学校における研究テーマを駆使したものであった。また、参観日という特別な日を活用することで保護者を巻き込んだ授業、校長先生所有の吹田作品を活用した実物鑑賞など様々な人との関わりや協力を得ることでより豊かな活動を展開させていった実践報告もあった。
このような実践報告から、「鑑賞遊び」が個を尊重し他者との豊かな交流の場を生み出すことのできる活動であることを確認するとともに、活動する子らの見方や考えに寄り添う教師の思いがその基盤を創り出すことなどを一層認識させられた。また、同一の鑑賞シートをフレキシブルに活用していく現場の教師力のなかに、これからの展望と機動力が存在することを実感させられた研究会ともなった。
3 パネルディスカッション
 指導要領改訂の要点の一つである「習得?活用」をキーワードとして現場教員と課題を共有することと、自分たちの鑑賞遊びの検証を、重ね合わせることが本研究会のねらいであった。そこで総覧型ではなく、発表を基点とする求心型のパネルディスカッションを設定した。濱口発表の根底にある生涯美術というコンセプトから、「図工室から生涯美術へ」と討議の流れを考え、またリレー発表の形ではなくフリートークで率直な関心を交換することにした。
指導要領改訂の要点の一つである「習得?活用」をキーワードとして現場教員と課題を共有することと、自分たちの鑑賞遊びの検証を、重ね合わせることが本研究会のねらいであった。そこで総覧型ではなく、発表を基点とする求心型のパネルディスカッションを設定した。濱口発表の根底にある生涯美術というコンセプトから、「図工室から生涯美術へ」と討議の流れを考え、またリレー発表の形ではなくフリートークで率直な関心を交換することにした。
(1)授業実践としての評価
山田:まず午前の授業研究会の話題から。題材は教師の力量や授業像と一体化して初めて成立する。研究会は実践を交流しており共感を覚えた。鑑賞シートが一人歩きに終わらず、フィードバックできるコミュニティを作ることを期待する。
赤木:岡山県立美術館の10数年にわたる学校連携においても、開発と普及の後の検証が直面する課題である。徳島とも交流したい。同じように見えながら異なる実践を生んでいる鑑賞シートの汎用性を検証されたい。
司会(竹内):濱口発表は、習得活用探求をテーマとするが、そこには教師の支援が後退していくという事柄も含まれているが。
山田:造形遊びではその年代の子どもたちが何を楽しむのかを重視するのだが、濱口さんの鑑賞遊びにも同じ印象を受ける。ただ、題材のポイントを探れないと難しい面もあり、ルールの柔軟性を高めても良いのでは。また、年齢に応じて高まっていく側面、系統性といった点はどうか。低学年から継続していった結果を期待する。
【まとめ】 即効性のある配布教材として開発を始めた鑑賞シートであったが、授業研究と交流の実践面をこそ評価された。どの子もが参加できるようにという鑑賞遊びの特性については、さらに学年を通した系統性や教科の中での位置づけを研究するよう提言を頂いた。
(2)教科としての見通し
結城:鑑賞教材の収集が教員の悩みであるという調査結果があり、鑑賞シートの果たす役割は大きい。吉野川市プレ大会における学校の蔵品を活かした例を見ても、普段の鑑賞環境の大切さを実感する。
鑑賞遊びは、自分の中に新しい価値を作り出す創造活動であり、知識詰め込みでなく、心が働いて知性と一体化する学び。持てる力を活用するという点で、改訂の時宜を得た研究。異なる学年で入口は同じでも良いと個人的には思う。学年により高まっていく内容が、授業と評価のポイントであり、鑑賞シート「指導の手引き」においても研究している。
赤木: 国吉康雄の教材開発では、学年に応じ活用の力がレベルアップしていくことを考えた。アートゲームなど方法は色々あるが、小学校から中学校まで共通事項的な柱はあるはず。
司会:国吉実践にある対話型鑑賞を、習得活用という面から見ると。
赤木:作品に戻ることが対話型においても重要。対話型にも、濱口発表での相互鑑賞に近い利点がある。作家・技法・歴史なども含めた議論を積極的に取り入れている。他教科での蓄積を活用できる場面が、高学年や中学生には必要。
【まとめ】 教師の役割像、授業像がまた異なる、対話を取り入れた鑑賞との共通点や、学年による高まりを意識した実践との比較から、研究の視点を頂いた。
(3)生涯美術 -美術批評、美術館活動との接点から
山木:鑑賞遊び、濱口授業の魅力は、どの人もアートに息吹をふきこむ運動の要素があること。アートを社会に浸透させることこそ美術教育の目的ではないか。知的な情報の取捨選択や評価には柔軟な心が必要であり、多様な見方を尊重する学びが理想。DBAEとも共通するのは、言葉による表現がときには教科の枠を越える。
大局的に見ても、海外から来たものではなく、地域をみすえた教師の立場からのユニークな鑑賞教育であり、新指導要領で求められる批評など鑑賞の指導の本道を行っている。皆さんも実際にやってみてほしいし、シーガルブログでのフィードバックもご覧いただきたい。
森:学校の習得活用と同じような実践が館にもあることをお伝えしたい。全ての子に鑑賞を楽しめる体験をさせることが目標。分析的な観察の他に、表現的に鑑賞する方法があるが、自分と作品を結びつけるために大切。それらを交流する活動は、鑑賞の本来的機能と言える。最近は学習後、手がかりを持って来館するケースも増えており、先生方と研究を深めたい。
主体性とは多義的である。内面の問題とコミュニケーションの双方から見ていきたい。鑑賞遊びが一人一人を大切にしている点に注目する。
【まとめ】 後盤、共同研究メンバーお二人からの話題提供をもって、研究の地盤、視野を再確認できた。日ごろはタスク実行型の会合の中で、ともすれば完成形を急ぐあまりメンバー同士の深い問題意識から息を合わせていくことがおざなりになる面もあったことを痛感させられた。
◇ ◇ ◇
会場の奥村高明教科調査官からは発表テーマの習得・活用・探求について、また鑑賞遊びの概念規定について鋭い批評が示された。特に、学習指導要領における「習得」と鑑賞遊びの「習得」と捉え方の差異の指摘は、今後のまとめ方についての示唆となるものであった。また、草の根的な立場で行ってきた鑑賞シート授業研究会の本質を私たち以上に見抜きこの活動の意義を唱えてくださったことは、これからの活動への大切なエールにしていきたい。東京学芸大学の山田一美先生からも、五感を活用した鑑賞活動や教師が手作りで行う作業の魅力についての意見を賜わった。
「鑑賞遊び」の報告により、鑑賞者の個を活かすことと、授業の普及の便を備えた両刃の「ルール」を主張したところ、実はルールを肉体化してきた実践の活動力と魅力が評価されたように感じました。実践を広めることに心血を注いできた企画者らの本意が励まされたことであり、研究会の機会を与えてくださったことに心から感謝します。
(報告:濱口由美/竹内利夫)
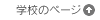
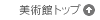
>> 徳島県立近代美術館 >> 学校のページ
 今回の研究発表では、改訂学習指導要領の基本方針でもある「習得・活用・探求」の学習指導の視点から、これまでの美術作品を対象とした鑑賞遊びにかかわる実践活動を捉え直すことで、「鑑賞遊び」が新しい教育課程における具現的な鑑賞プログラムとして様々な可能性を持つことを示した。また、生涯美術への素地を育む鑑賞活動としての「鑑賞遊び」のスタンスを表明することで、2部のパネルディスカッションへの問題提起とした。
今回の研究発表では、改訂学習指導要領の基本方針でもある「習得・活用・探求」の学習指導の視点から、これまでの美術作品を対象とした鑑賞遊びにかかわる実践活動を捉え直すことで、「鑑賞遊び」が新しい教育課程における具現的な鑑賞プログラムとして様々な可能性を持つことを示した。また、生涯美術への素地を育む鑑賞活動としての「鑑賞遊び」のスタンスを表明することで、2部のパネルディスカッションへの問題提起とした。 1時間目は、脇本正久教諭の5年生児童による「音のかくれんぼ」の実践報告。子どもたちの評価活動を鑑賞遊びの活動に組み込むことで、相互鑑賞の場がより意欲的な活動となることや批評的な見方も高まることを提言された。
1時間目は、脇本正久教諭の5年生児童による「音のかくれんぼ」の実践報告。子どもたちの評価活動を鑑賞遊びの活動に組み込むことで、相互鑑賞の場がより意欲的な活動となることや批評的な見方も高まることを提言された。 指導要領改訂の要点の一つである「習得?活用」をキーワードとして現場教員と課題を共有することと、自分たちの鑑賞遊びの検証を、重ね合わせることが本研究会のねらいであった。そこで総覧型ではなく、発表を基点とする求心型のパネルディスカッションを設定した。濱口発表の根底にある生涯美術というコンセプトから、「図工室から生涯美術へ」と討議の流れを考え、またリレー発表の形ではなくフリートークで率直な関心を交換することにした。
指導要領改訂の要点の一つである「習得?活用」をキーワードとして現場教員と課題を共有することと、自分たちの鑑賞遊びの検証を、重ね合わせることが本研究会のねらいであった。そこで総覧型ではなく、発表を基点とする求心型のパネルディスカッションを設定した。濱口発表の根底にある生涯美術というコンセプトから、「図工室から生涯美術へ」と討議の流れを考え、またリレー発表の形ではなくフリートークで率直な関心を交換することにした。