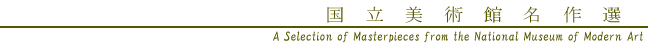
Ⅰ.「洋画」誕生
 我が国の近代洋画史の始まりは、江戸幕府が安政3(1856)年に蕃書調所を設立し、翌年に絵図調方を設けて川上冬崖を絵図調出役としたのが始まりと言われています。明治初期の我が国の洋画壇にはいくつかの私塾がありましたが、これらの私塾は、未だ材料・用具・技法等が未熟で本格的な油絵には遠く、独学独歩の状態だったと言えます。
我が国の近代洋画史の始まりは、江戸幕府が安政3(1856)年に蕃書調所を設立し、翌年に絵図調方を設けて川上冬崖を絵図調出役としたのが始まりと言われています。明治初期の我が国の洋画壇にはいくつかの私塾がありましたが、これらの私塾は、未だ材料・用具・技法等が未熟で本格的な油絵には遠く、独学独歩の状態だったと言えます。明治政府は、明治9(1876)年に我が国最初の官立美術学校として工部美術学校を設立し、画学教師としてアントニオ・フォンタネージを雇い入れ、本格的な洋画教育を始めています。当時の画学生徒は合計31名で、主な生徒に小山正太郎、松岡寿、印藤真楯、浅井忠らがいましたが、明治11年にフォンタネージが工部美術学校を辞任すると、小山正太郎、浅井忠、印藤真楯ら多くの生徒が連袂退学して十一会を結成しました。十一会は、我が国で最初の在野洋画研究団体となりましたが、明治22年には明治美術会へと展開しています。
〈明治26年、ラファエル・コランから印象派風の外光を取り入れた作風を学んだ黒田清輝がフランスから帰国。当初は、明治美術会に参加していましたが、脂のような暗い褐色の色調が主流で「脂派」または「旧派」と呼ばれていた明治美術会と対立し、明治29年、久米桂一郎や藤島武二らと白馬会を結成し、「紫派(外光派)」または「新派」と呼ばれました。同年、東京美術学校に西洋画科が新設されると、黒田が指導者として招かれ、東京美術学校からは石井柏亭、山下新太郎、南薫造ら数多くの画家が育っています。
【図版】 浅井 忠 〈編みもの〉 明治34年 京都国立近代美術館蔵