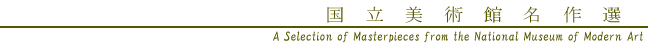
Ⅱ.「洋画家」たちの花開く個性
 明治40年、明治政府は美術振興策として文部省美術展覧会(文展)を設置しました。文展は、諸団体の対立を緩和して、多くの作家達が競う初めての官制の公募展でしたが、以後、帝国美術展覧会(帝展)、新文展、日本美術展覧会(日展)と続いています。設置当初から新旧対立の様相を示していた文展でしたが、文展発足以来、在野の美術団体が次々と結成され、洋画家たちの個性が花開く時代と言われました。大正元(1912)年、岸田劉生や萬鉄五郎らがフュウザン会を結成、翌年解散すると、岸田は草土社を結成し、北方ルネッサンスの細密描写に習い、神秘的な世界を創り上げています。大正3年、石井柏亭、梅原龍三郎、山下新太郎ら洋画部の新傾向の画家達が審査方法に反発し、二科会を結成しています。その後二科会には、安井曾太郎、小出楢重、里見勝蔵、東郷青児、国吉康雄、藤田嗣治らが会員となり、文展と対立した最初の在野団体として、以後の画壇に大きな影響を与えました。昭和5(1930)年、児島善三郎や里見勝蔵らが二科会を退会して独立美術協会を結成し、新しい日本の洋画の確立を目指しました。
明治40年、明治政府は美術振興策として文部省美術展覧会(文展)を設置しました。文展は、諸団体の対立を緩和して、多くの作家達が競う初めての官制の公募展でしたが、以後、帝国美術展覧会(帝展)、新文展、日本美術展覧会(日展)と続いています。設置当初から新旧対立の様相を示していた文展でしたが、文展発足以来、在野の美術団体が次々と結成され、洋画家たちの個性が花開く時代と言われました。大正元(1912)年、岸田劉生や萬鉄五郎らがフュウザン会を結成、翌年解散すると、岸田は草土社を結成し、北方ルネッサンスの細密描写に習い、神秘的な世界を創り上げています。大正3年、石井柏亭、梅原龍三郎、山下新太郎ら洋画部の新傾向の画家達が審査方法に反発し、二科会を結成しています。その後二科会には、安井曾太郎、小出楢重、里見勝蔵、東郷青児、国吉康雄、藤田嗣治らが会員となり、文展と対立した最初の在野団体として、以後の画壇に大きな影響を与えました。昭和5(1930)年、児島善三郎や里見勝蔵らが二科会を退会して独立美術協会を結成し、新しい日本の洋画の確立を目指しました。一方、大正12年の関東大震災前後から、前衛美術が盛り上がりを見せています。ベルリンで哲学を学び前衛美術に転向した村山知義の呼びかけて集まったマヴォや、古賀春江らのアクションなど、前衛美術集団が次々と結成されては解散、そして新たな結成とめまぐるしく展開しています。二科会では、シュルレアリスムやキュビスムの影響を受けた東郷青児や川口軌外、抽象表現を目指した山口長男や斎藤義重などが九室会を結成し、前衛画家として活躍しています。
また、国内の活動だけでなく、海外を活動の拠点にする画家も現れました。戦後フランス国籍を得た藤田嗣治はパリ美術界の寵児であり、日本画の技法を生かして描いた裸婦は高く評価されました。新興国アメリカはモダニズムの最前線にあり、アメリカに渡った国吉康雄、石垣栄太郎、清水登之などは、社会に関心を寄せ、労働者や庶民の暮らしを描いています。
【図版】 岸田劉生 〈麗子弾絃図〉 大正12年 京都国立近代美術館蔵