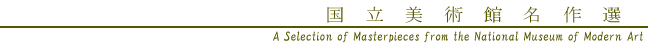
Ⅲ.日本画-「洋画」との並立
新しい日本画創造の試みは、アーネスト・フェノロサや岡倉天心らの活動に始まっています。天心は東京美術学校の開校を導き、明治31年、新しい日本画創造を目指す美術団体として日本美術院を創設しました。美術院の三羽烏と呼ばれた横山大観、菱田春草、下村観山らは、西洋絵画のような自然な空気感を色彩のにじみによって表現する方法で、いわゆる朦朧体といわれた技法を生み出しています。一方、京都においては、竹内栖鳳がヨーロッパを視察後、雅号を棲鳳から西の字を含む栖鳳にあらため、光や空気、立体感などの西洋絵画の表現を積極的に日本画に取り入れています。また堂本印象は、イタリア・ルネサンス絵画の趣をたたえた日本画を制作しています。
 文展から帝展、そして新文展へと改組する官展で、竹内栖鳳、上村松園、堂本印象、廣島晃甫らが活躍しています。大正3年、一時消滅していた日本美術院が再興日本美術院として復活し、今村紫紅、安田靫彦、速水御舟、奥村土牛らが活躍しています。大正7年、京都では国画創作協会が結成され、土田麦僊、入江波光、榊原紫峰ら若い画家たちが活躍し、さらに飛躍した新しい日本画に挑戦しています。他方、秦テルヲなどは会派に属さず、大正デカダンスの風潮から生まれた個性的な日本画を描いています。昭和4年には、川端龍子が再興日本美術院を退会して青龍社を結成し、会場芸術という新しい形式を追求しています。
文展から帝展、そして新文展へと改組する官展で、竹内栖鳳、上村松園、堂本印象、廣島晃甫らが活躍しています。大正3年、一時消滅していた日本美術院が再興日本美術院として復活し、今村紫紅、安田靫彦、速水御舟、奥村土牛らが活躍しています。大正7年、京都では国画創作協会が結成され、土田麦僊、入江波光、榊原紫峰ら若い画家たちが活躍し、さらに飛躍した新しい日本画に挑戦しています。他方、秦テルヲなどは会派に属さず、大正デカダンスの風潮から生まれた個性的な日本画を描いています。昭和4年には、川端龍子が再興日本美術院を退会して青龍社を結成し、会場芸術という新しい形式を追求しています。戦後まもなくして、青龍社や再興日本美術院が展覧会を再開し、昭和21年に文部省主催の総合美術展覧会として日展が開催され、院展では小倉遊亀、平山郁夫、森田曠平らが、日展では池田遙邨、杉山寧、髙山辰雄らが活躍しています。
(「広島晃甫」の人名表記を「廣島晃甫」に改めました。)
【図版】 廣島晃甫 〈青衣の女〉 大正10年 東京国立近代美術館蔵