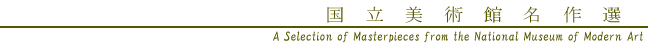
Ⅳ.「洋画」を超えて -「戦後美術」という名のもとに
昭和20年8月に終戦を迎えると、戦時中に解散を命じられていた各美術団体の再発足と再編が始まりました。東郷青児らによる二科会の再発足、梅原龍三郎らによる国画会の再発足、須田国太郎らによる独立美術協会の再発足、斎藤義重や北脇昇らによる美術文化協会の再発足、麻生三郎らによる自由美術家協会の再発足、瑛九らによるデモクラート美術家協会の結成、猪熊弦一郎らによる新制作協会の結成など、従来の美術団体の再発足とともに新しい美術団体が数多く結成されるなど、戦前に比べて多様な展開を見せています。昭和26年、日本の戦後美術に一つの転機をもたらしたと言われた「サロン・ド・メ日本展(現代フランス美術展)」が開催され、この年に始まったサンパウロ・ビエンナーレや翌年のヴェネツィア・ビエンナーレに日本の作家達が作品を発表し、国内においても毎日新聞社主催の日本国際美術展が開催されるなど、美術界の国際化が一段と進めらました。
昭和29年、吉原治良を中心に、前衛美術家の集団として具体美術協会が結成され、野外展、舞台でのイベント、屋外でのパフォーマンスなど先鋭的な活動を展開して、戦後の美術界に衝撃を与えました。一方、堂本尚郎はパリに居て直接アンフォルメル運動の洗礼を受けてアンフォルメル運動に身を投じ、田淵安一は「サロン・ド・メ」に出品するなどフランスを拠点に活動しています。現代美術の拠点の一つとして知られるニューヨークでは、数多くの日本人画家が滞在して制作活動を行っていますが、猪熊弦一郎は最も初期の1955年からニューヨークに滞在し、ニューヨークの町並みを記号のように単純化しながら円や直線を基本として描いています。
(専門学芸員 仲田 耕三)
(徳島県立近代美術館ニュース No.71 掲載)