版画の鑑賞眼
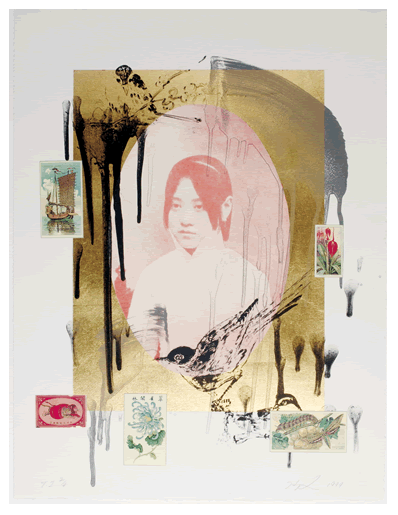 「版画は技法がわからないから鑑賞が難しい」という声を聞くことが少なくありません。また、「これも版画なのですか」というのもよくお受けする質問の一つです。確かに、製版や刷りなどのプロセスを経て生み出される版画の画面には、塗り重ねの筆跡や筆圧などが直接見えることはなく、少しなぞめいた技術の妙を思わせる時があります。
「版画は技法がわからないから鑑賞が難しい」という声を聞くことが少なくありません。また、「これも版画なのですか」というのもよくお受けする質問の一つです。確かに、製版や刷りなどのプロセスを経て生み出される版画の画面には、塗り重ねの筆跡や筆圧などが直接見えることはなく、少しなぞめいた技術の妙を思わせる時があります。
けれども考えてみれば、幾多の工夫と洗練が薄い画面の上にたたみ込まれた版画の表現は、筆やペンとはまた違った、一種の作家のタッチであると言うこともできます。版材や手順の特性と取り組む中で作家たちはイメージを絞り込み、そこで捨て去るものがあり、逆にクローズアップされるものがあり、世界に二つとない自分だけの方法論を見出します。その意味で「版」は常にハンドメイドなのです。
そして、そのような制作が工房というサポート体制の中で、他者との共感的な試行錯誤を経て、生み出されるというのは、作家にとっては実にエキサイティングな体験であるはずです。版画は時代の複製技術と共に発展しながらも、常に作家の個人的な世界を、伝統から最新技術まで広大な可能性へ誘う独自の役割を果たしてきたと言えましょう。そのような版画の面白さは、デジタル画像全盛の時代になっても、かえって人と技術の関係を再構築する役割をますます開拓していくように思われます。
文化を映す鏡
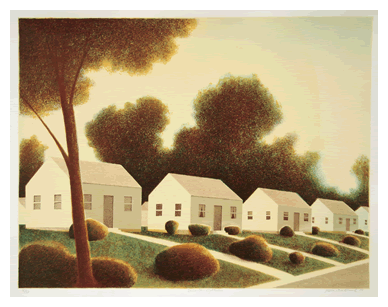 さらに、版画のもう一つの特性は、写真や映像に限らずあらゆるイメージを、編集したり、変化させたりといったことが得意な分野だという点です。おのずとこの領域には、イラストやデザインに似た、時代の文化を映し出す要素が可能性として横たわっています。本展に出品された多くの作品が、様々な作家自身の文化的背景を強く感じさせます。多元的なアメリカ文化のありようがそこに示されていると言うこともできるでしょうし、それはまた、版画領域の特性とも言えるものです。本展が、ただ版画の様々を紹介するだけで終わるのではなく、時代を映す鏡、それは他ならないアートの役割と言えますが、そのような視点から文化的対話としての展覧会体験が版画を通して生まれることを願っています。
さらに、版画のもう一つの特性は、写真や映像に限らずあらゆるイメージを、編集したり、変化させたりといったことが得意な分野だという点です。おのずとこの領域には、イラストやデザインに似た、時代の文化を映し出す要素が可能性として横たわっています。本展に出品された多くの作品が、様々な作家自身の文化的背景を強く感じさせます。多元的なアメリカ文化のありようがそこに示されていると言うこともできるでしょうし、それはまた、版画領域の特性とも言えるものです。本展が、ただ版画の様々を紹介するだけで終わるのではなく、時代を映す鏡、それは他ならないアートの役割と言えますが、そのような視点から文化的対話としての展覧会体験が版画を通して生まれることを願っています。
(主任学芸員 竹内 利夫)
(徳島県立近代美術館ニュース No.66 掲載)