
1924年、詩人アンドレ・ブルトンを中心にシュルレアリスム運動が起こります。あらゆる固定観念や理性的な思考から解放された、本当の意味での自由な表現を目指したこの運動は、偶然や夢、無意識のような世界に積極的に注目しながら、思いもかけない表現を生み出していきました。これに出会ったピカソも、形がゆがんだり、獣に変身した人物や、ものの輪郭線が入り組んで混線してしまったような姿など、不思議な作品を制作していきます。
<フランコの夢と嘘>は、1936年に起こった、スペイン人民戦線政府に対してフランコ将軍率いる軍部が行った反乱のために困窮した人民戦線政府を支援するために制作された版画です。それぞれ葉書大に区切られた9つの区画に、まるで漫画のように、虐殺された人民や、弾圧するフランコの姿が、滑稽な化け物や、ゆがみ苦しむ異形の姿で描かれています。 このように人物を歪形(デフォルメ)させる描き方は、愛する女性たちにも及びます。油絵ですが<ドラ・マールの肖像>や<赤い枕で眠る女>は、ピカソの恋人がモデルとなっています。

このコーナーでは、視点を少し変えて、ピカソが描いた様々な顔をごらんいただきます。<カルメン>は、メリメ作で、作曲家のビゼーによるオペラでも有名な『カルメン』に寄せた銅版画による挿絵です。スペイン出身のピカソは、生涯を通じて闘牛に深い関心を寄せていました。情熱的でエキセントリックな女性カルメンを巡る悲恋の物語のクライマックスの場面も闘牛場です。この人気ある物語を、簡潔な線で描かれた30枚を超える個性豊かな顔で表した興味深い作品です。
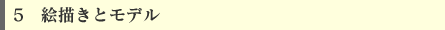
ピカソは、絵描きとモデルの関係をテーマに多くの作品を残しています。そこに描かれた絵描きの姿は、おそらくピカソ自身の自画像でもあります。特に晩年は日付を記しながら大量にこの「画家とモデル」のテーマによる版画を制作していますが、そこには、おそらく日記のような意味合いもあったのでしょう。<流砂>は、1960年に亡くなった詩人、ピエール・ルヴェルディの最後の詩にピカソが寄せた挿絵です。それらは「画家とモデル」をテーマとする作品のうち、1964年と65年に制作された版画10点から成っています。ここには、晩年のピカソらしい奔放な表現が見られますが、晩年の「画家とモデル」の作品群の多くが、エロティックな欲望を生き生きと伝えてくるのに比べて、<流砂>の作品群は、いくぶん禁欲的な緊張感も感じさせます。ルヴェルディの詩は、一人の詩人が自らの人生を振り返り、締めくくるものでした。全てのものがいつかは死に絶えるように、詩人にも必ず死は迫ってくる、こんな当たり前のことが、死に直面した詩人の胸をよぎります。さて、ここに老画家ピカソのどのような思いを見ることができるでしょうか。
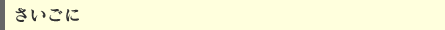
ピカソは生涯に、銅版画を中心として、リトグラフや新素材であったリノリウム板を使ったリノカットなど、あわせておよそ2,000点にも及ぶ膨大な版画を残しています。この展覧会で紹介する版画は、銅版画ばかりですが、ピカソがもっとも熱心に取り組んだのも銅版画でした。エッチングやドライポイント、アクアチントなど、様々な銅版画技法を駆使した版画家ピカソの一面をごらんいただきたいと思います。
また、ピカソは、一つの版画作品を仕上げるために多くの試作を行ったり、完成までに何度も手を入れています。今回の展覧会では、その段階をたどることのできる作品があります。<三人の女III>については2点の、<フランコの夢と嘘>(2点組)については7点の、それぞれの段階刷りをあわせて展示します。ピカソの版画制作のプロセスを伺い知ることのできる貴重な機会となることでしょう。
会場には何点かの油絵も展示しています。加えて、ピカソに関連する書籍や絵本を閲覧するコーナーも設けています。会期中には展示解説や講座の他にも、ピカソに関する絵本の読み聞かせや、ピカソからインスピレーションを受けた音楽のコンサートも予定しています。この機会に、改めてピカソのことを知っていただく絶好の機会になることを願っています。
(主任学芸員 友井伸一)
copyright:徳島県立近代美術館2006