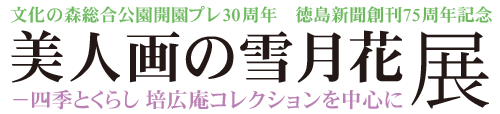NEWS
徳島県立
近代美術館
ニュース
美人画の雪月花 -四季とくらし 培広庵コレクションを中心に
上村 松園《桜狩の図》1935(昭和10)年頃 絹本着色 培広庵コレクション
この記事は、徳島県立近代美術館が発行する季刊誌「徳島県立近代美術館ニュース」110号に掲載されたものです。
はじめに
いよいよ来年にせまった「東京2020オリンピック・パラリンピック」。オリンピックはスポーツだけではなく「文化の祭典」でもあります。そして2020年は文化の森総合公園開園30周年。近代美術館も開館30周年を迎えます。このメモリアルイヤーを1年後に控え、令和となって最初となる近代美術館の特別展は「日本文化の発信」を目指した日本画の美術展です。テーマは「美人画」です。
日本の伝統的な絵画では、風景や花鳥、肖像、歴史や物語の場面、仏画、風俗など様々なモチーフが描かれてきました。女性もその一つです。日本美術の中で女性が描かれた例としては、高松塚古墳の壁画をはじめ、ずいぶん古くから見られます。また、桃山や江戸の頃の風俗画、浮世絵には多くの作例が挙げられます。
やがて明治の終わりから大正の頃になると、女性の理想的で典型的な美しさを、その時代の風俗、風潮においてとらえた「美人画」というジャンルが、「日本画」の一分野として確立してきました。ちなみに「日本画」とは、「岩絵具などの顔料や墨を用いて、和紙や絹の上に描く」という日本伝統の技法を受け継ぎながら、明治以降の近代化の中で、新たに発展してきたものです。
さて、この「美人画」が最も輝きを放ったのは大正、昭和初期といわれています。本展ではこの時期に焦点を当てて、国内屈指の近代美人画コレクションとして知られる「培広庵コレクション」に、当館等の所蔵作品を加えてご紹介します。優美な作品で美人画の世界をリードした東の鏑木清方、西の上村松園をはじめ、伊東深水、北野恒富、紺谷光俊らの作品を、「四季-春夏秋冬」、「芸事・踊り」、「個性的な表現へー人間を見つめる」、[物語・歴史など」の4コーナーでご覧いただきます。
四季 ―春夏秋冬

《採果図》
春は散る花を愛で、夏は浴衣で涼をとり、秋には野に遊び、冬の雪景色にたたずむ女性たち。このコーナーでは、四季をテーマにご覧いただきます。
上村松園(うえむら しょうえん)の〈桜狩の図〉では、日傘を差して振り袖を着た京都の令嬢がお供の女性と一緒にお出かけする華やいだ様子が描かれています。着物の柄からも桜の季節であることがわかります。上村松園は京都の四条派の流れをくみ、伝統に近代的な感性を加えた優美な画風で知られる女流画家。近代美人画の代表作家の一人です。
この松園と並び称されるのが鏑木清方(かぶらき きよかた)です。〈夏姿〉では、朝顔の描かれた団扇を手にした女性が、向こうが透けるような暖簾から顔をのぞかせています。薄物の着物には燕子花(かきつばた)。初夏なのでしょうか、さわやかな涼しさを感じます。
紺谷光俊(こんたに こうしゅん)の〈採果図〉では若い女性と幼い少女が葡萄を収穫しています。繁栄や豊穣を祈って古来より描かれてきた「樹下美人図」の一つで、「葡萄」は子孫繁栄の吉祥のしるし。小袖に細めの帯、髪を束ねて後ろに垂らした女性の姿は、桃山から江戸初期の風俗を思わせます。少女の持つ籠には西洋風の陰影表現も見られます。
愁いを帯びた女性像で大正時代の流行作家となった竹久夢二(たけひさ ゆめじ1884-1934年)。〈投扇興〉では、蝶に見立てた的を扇で狙う遊びに興ずる二人の女性が描かれています。S字を描いてしどけなく座る姿や、腰を浮かせて的を狙う姿には、ほのかな色気が漂います。的には春の桜。向かって左の着物には夏の波、右には秋の蜻蛉。そして投扇興は新年の季語となり、ここに四季が一巡りします。
四季折々にうつりかわる風情のなかで日本女性の美しさをご堪能下さい。

《投扇興》
芸事・踊り

《素踊》

《阿波踊》
美人画の中には、芸事や舞妓、芸妓を描いた作品が多数あります。山川秀峰(やまかわ しゅうほう)の〈素踊〉は日本舞踊の花柳寿美(はなやぎ すみ)を、小早川清(こばやかわ きよし)の〈名技市丸〉は浅草の人気芸者だった市丸をモデルとしています。ほかにも、村上華岳(むらかみ かがく)、土田麦僊(つちだ ばくせん)、島成園(しま せいえん)らが描く女性の姿には、優雅さや気品の中に秘められた情熱や色気を感じます。またここでは、昭和初期に徳島を取材し、「阿波よしこの」の名手で知られた「お鯉さん」をモデルに描いたとされる、北野恒富(きたの つねとみ)の〈阿波踊〉も展示しています。
個性的な表現へ ―人間を見つめる

《傘の舞妓》
美人画が最盛期となった大正から昭和初期は、画家の個性的な表現への取り組みが拡がった時期でもありました。それは大正デカダンス(退廃的、耽美的)とも言われます。甲斐庄楠音(かいのしょう ただおと)、岡本神草(おかもと しんそう)、谷角日沙春(たにかど ひさはる)らの作品は、ここまで見てきた美人画とは異なった印象を与えるかも知れません。美の基準の多様性を感じながら、女性を人間としてリアルにとらえた表現をお楽しみください。
物語・歴史など
物語や歴史などを画題とする絵画にも美人画と言える作品が多数見られます。最後のコーナーでは『平家物語』、『太平記』、『好色五人女』などの物語や、和歌、俳句、あるいは浄瑠璃、謡曲など、日本の文学や芸能に想を得た絵画をご紹介します。
さいごに
ここで見られる女性の姿や風俗は、今では遠い昔のようです。とくに若い方には懐かしさを通り過ぎてほとんど未知の世界かも知れません。本展ではそんな日本の風俗や情緒と出会うことができます。そして、もし着物に興味を引かれた方は、思い切って和装で来場くださると、割引料金で入場いただけます。知っているようで知らない日本の文化、「着物」を再発見する絶好の機会にもなるでしょう。
さらに本展には当館の所蔵作品も出品しています。「20世紀の人間像」を最大の特徴とする徳島のコレクションの新たな一面を、「美人画」という視点から見直していただければと思います。
大正期前後の「美人画」の流行は、明治以降の世の中の近代化の中で、日本の伝統と新しい西洋の価値観がせめぎ合い、日本のアイデンティティが大きく揺らぎながら、日本とは何か、ということが切実に問われた時代を背景としています。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて国際化が進む中、この展覧会が、日本の美や伝統について改めて思い巡らす機会となれば幸いです。
友井伸一(徳島県立近代美術館 上席学芸員)
徳島県立近代美術館
〒770-8070
徳島市八万町向寺山 文化の森総合公園内
TEL: 088-668-1088
FAX: 088-668-7198