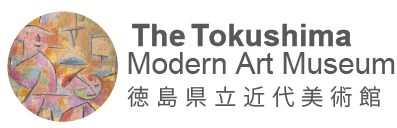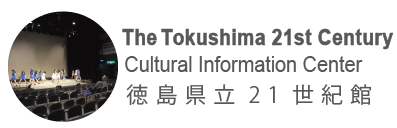受賞されたみなさま、おめでとうございます。参加されたみなさま、お疲れさまでした。
徳島県立近代美術館の森方功です。
私からは、チャレンジの内容面から気付いたことを、受賞されなかった方の作品にも触れつつお話しさせていただけたらと思います。
誰にとってもチャレンジすることは、制作以外の生活や人生と関わってくると思うのですが、それが作品や展示から見えてくるのがこの芸術祭の魅力です。
チャレンジ奨励賞を受賞された「住友知江」さんは、自然素材の服を探していたときに麻の糸と出会ったそうですね。そして、毎月徳島から東京に通って技術を身につけ、途絶えようとしていた大麻草の糸をつむぎ、仲間をつくりながら、布づくりができるところまで制作を進めています。糸の美しさとともに、試みてきた模索の過程が伝わってくる展示だったと思います。
住友さんのチャレンジは、人生の転換を感じさせる力強いものがあるのに対し、なにげない日常をすくい上げるような作品を出品されたのが、「あ」のコーナーの 「景」 さんです。2歳のこどもさんと海に行って拾った貝殻や珊瑚のかけらを瓶に入れ、こども服にドローイングをして展示しています。家族の「あっという間になくなってしまう時間」を記録しようとする気持ちがなければ生まれなかった、ほのぼのとした雰囲気のある作品です。これもチャレンジに他ならないなと思いました。
そして、「森節子」さんの着物をドレス風に着付ける提案も興味深く感じました。着物を切ったりリフォームしたりせず、着付けによって和と洋を結びつけた装いを提案しています。「徳島から日本中、世界中へ」広げたいとパンフに書いてありますので、オリジナリティーを確かめつつ、多くの人が面白く感じ、受け入れられるよう、さらなるチャレンジを期待したいと思います。
他に私は、「永田広志」さん、「穴山千代子」さん、「尾田稔子」さんの作品などが印象に残りました。
審査員の会議のなかで、チャレンジした結果、見た人に明るい力が広がっていく、そこが大事だという意見が出ました。
誰もが創造的に自己実現できることを願っているわけですが、日々の暮らしのなかではさまざまな制約もあって、なかなか思うようにはいきません。しかし、よりよく生きたいという気持ちがあるからこそ、他の人のチャレンジに刺激され、元気が伝わっていくのだと思います。
制作した人の思いの強さ、それを形にする努力、そしてそのよさを他の人と共有する力が集まると、チャレンジが多くの人に伝わっていくのかもしれません。
以上簡単ですが、私の講評に替えさせていただきます。ありがとうございました。