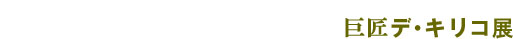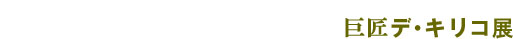| 古典絵画の研究
 謎めいた作品の印象が強いデ・キリコですが、この展覧会には古典的と言っても良い作品も出品されています。例えば、〈裸婦〉(1942年頃)はルーベンスの〈森の中の裸婦〉の研究の成果と指摘されています。
謎めいた作品の印象が強いデ・キリコですが、この展覧会には古典的と言っても良い作品も出品されています。例えば、〈裸婦〉(1942年頃)はルーベンスの〈森の中の裸婦〉の研究の成果と指摘されています。
彼が突如こうした傾向の作品を描き始めたのは1920年頃からです。この変化はまた、違った意味でのデ・キリコの「謎」と言えます。
この時期のヨーロッパは第一次大戦後の秩序回復へ向かおうとする傾向があり、そのために古典的なものが好まれました。デ・キリコの変化に、この時代背景との関連が指摘されることもあります。
一方、どの程度時代の影響があったのかはともかく、彼は回想記の中で次のように述べています。
1919年にローマの美術館でティツィアーノの絵を見ていた時、突然の啓示があった。
それは、偉大な絵画の条件は描かれたイメージにあるのではなく、絵の具や溶き油といった画材の質にあるということに気付いたと言うことです。
古典的に見える作品を描いたのも、かつて用いられた画材を確かめるために、その時代に描かれたようなイメージを選んだと言うことなのです。
この後もずっとデ・キリコは、美術館に残るような古典絵画の画材の質を研究し、自らの作品に反映させ、古典絵画のように普遍的な価値を持ったものにしようとしたのです。
異なった制作年
今回の出品作品はデ・キリコ後期の作品が中心になっていますが、作品中に書き込まれた制作年と作品キャプションに記されている制作年が違って、ずいぶん古い年になっていることがあります。これは、作品の書き込みが故意に変更されているのです。例えば〈不安を与えるミューズたち〉の作中に記されている制作年は1924年ですが、作品キャブションは1974年となっています。
「謎」と言うよりも悪い冗談のように思えます。しかし、このことは、その時々で制作した作品の制作年を遡るとすれば、作品の評価は変わるのだろうか、というデ・キリコからの問いかけではないでしょうか。
近代から現代にかけての美術の流れでは、新しい、これまで見たことのない作品を生み出すことが良しとされてきました。そのことによって、優れた作品が生まれたことも確かです。それでは、その時々に生まれた「新しい」作品の良さは、新しいが故のことだったのかという。 |