内なる目覚め

インスタレーション<内>の中のハンス・ペーター・クーン
(2005年 オーデンセ/デンマーク)
垣根を越えるクリエーター
ハンス・ペーター・クーン(1952- )は、1970年代、ベルリンの主要劇場の一つ、シャゥビューネで舞台に関わる仕事を始めました。その後、劇場の舞台に関わるだけにとどまらず、インスタレーションやダンス、パフォーマンスなど、ジャンルを飛び越え、抜きんでた表現を次々と発表し、評価を高めてきました。それは、舞台の仕事でベッシー賞を、美術の仕事でベネチア・ビエンナーレ金獅子賞を受賞するなど、数多い受賞歴からも明らかでしょう。その後も、音楽を芯に据えた、彼のインスタレーションは、表現の新たな可能性を切り拓き、時代を牽引し続けてきました。
中央の場
ご記憶の方もいらっしゃると思うのですが、当館では2004年1月から3月にかけて「シーニック・アイ 美術と劇場」という展覧会を開催しました。これは、劇場に関わる仕事をしている現代ドイツの美術家たちの作品を展覧した、世界に誇る劇場都市・ベルリン発信の企画として、総重量約8トンのパッケージで徳島に上陸しました。展示室には、劇場に関わる美術のさまざまな仕掛けがしつらえられ、そのテーマを絞った内容は、ベルリンを中心とする現代ドイツの劇場文化のありようと美術との関わりを強く意識させただけでなく、隣接する表現の領域がお互いに刺激し合って、高め合う効果をもたらす好例として紹介されました。
この会場の中で、規模は小さいながら、とてもスケールの大きな内容をもった作品がありました。それが、ハンス・ペーター・クーンの作品でした。<中央の場(Mittelplatz)>というタイトルの音響インスタレーションの作品は、130cm四方の木製の板の中央に据えてある椅子に鑑賞者が腰を下ろし、フロアの四隅に据えられたスピーカーから聞こえてくる音(音楽)を体感(鑑賞)するというものでした。タイトルにある「中央の場」に鑑賞者は据えられ、鑑賞者であると同時に、他の鑑賞者から見ると、作品を完成させる大切な要素にもなりました。ライトアップされた中央の椅子に人が腰掛けると、確かに作品はより美しく見えました。奇妙な仕掛けは、正面の柱に立てかけられたアクリルガラス板の存在でした。
鑑賞者はまず、耳を澄まし、感覚をとぎ研ぎ澄ませなければなりません。聞こえてくるのは間遠な音。おそらく水の滴る音。これが壮大な物語の描写の始まりでした。水の音は次第に激しさを増してゆきます。ぽつりぽつりと降っていた雨が、本格的に降り出し、ある瞬間、その雨音は、鑑賞者自身に浴びせられる盛大な拍手の音に様変わりしていることに気づきます。その瞬間、鑑賞者は、舞台の上の人となり、舞台の上にいる自らの姿を、目の前のアクリルガラスの中に見いだすのです。なんという見事な演出でしょう。これが鏡であったなら、目の前にくっきりと見える自分の姿を見て、音への集中は中途半端なものになったかもしれません。向こう側が透けて見えるアクリルの表面に、柔らかく映り込んでいる自分の姿は、すぐにはそれと気づきません。しかし、音に耳を傾ける中、それは徐々に私たちの意識にのぼってきます。自分が、舞台慣れしていないピアニストか一人語りの役者のようにも見えたものでした。そうする間にも、音の描写は続きます。やがて集まってきた雨粒が小さな流れとなり、河に注ぎ込み、最後は雄大なスケールで大海へと流れ込むのでした。2立方メートルほどの空間をすっかり舞台にしてしまったこの作品は、作品のスケールは、そのものが空間に占める物量でないことを改めて感じさせ、同時に、音の持つ大きな可能性を感じさせました。
Lichterfeld F60
クーンはまた、格別に大きなスケールの作品も制作しています。2005年度の冬。真冬のベルリンを訪ねたとき、クーンは「できるならば<F60>を観て行くのがいいだろう」と言いました。そこで、コペンハーゲンから戻ってきたクーンをテンペルホフ空港に出迎えた後、車で向かったのがF60。とにかく曠野に立っている巨大な作品であるから、ということを聞いていましたが、本当に、こんなところに作品があるのかといぶかしく思われるほど、ベルリンから南の方角に車を走らせた頃に、それは出現しました。真っ暗闇の中、その巨大な光の存在は、不思議な感覚を呼び覚ましました。車を停めて近づいてみると、目の前の大きな作品は、首を大きく振らないと、視界の中に収まりきらないばかりか、作品を走り抜けるような音は、彼方の暗闇に吸い込まれるように突き進んでゆくものでした。
私たちの訪問のために、わざわざ作品に点灯してくれていた管理技師の男性の、親切な案内により、管理棟の階段を上って、少し高みにあるベランダから再び、作品を眺め渡した時、寒さも忘れるほど心が震えました。まさにそれは、曠野の劇場そのものでした。
さまざまな色の光が点在するのは、かつて炭坑の花形の働き手だった石炭採掘のための巨大な機械。近代の産業遺産といわれるものでした。もう使われなくなった、その長いアームに取り付けられたベルトの上を、どれだけの量の石炭が運ばれたことでしょう。この使われなくなった機械が、私たちに真向かう巨大な舞台装置となったわけです。これは、おそらく単体では、世界で一番大きなパブリック・アートだと言ってよいのではないでしょうか。
近代産業遺産を現代のアートを用いて、新しい文化的産物に仕立てるというやり方は、有名なルール工業地帯でも大がかりに取り組まれたプロジェクトですが、ベルリン郊外のこの地でも、この産業遺産を軸に、人々の休暇のための、人工池を有するテーマパークとして整備されつつあるそうです。産業とアートとレジャーの融合とは、まさに新しいスタイルのものでしょう。近い将来、人工池に浮かぶヨットの上から、クーンの作品が観られるようになるかもしれません。
2005年のオーデンセにて
2005年にデンマークのオーデンセで、クーンが取り組んだ個展のタイトルは、<内/外>。それは、美術館の内と外の空間を駆使したプランで、3つの主要な作品によって構成されていました。
まず、会場となった美術館の建物の正面に足場が組まれ、60台のモニターが設置されました。これが<外>。それぞれのモニターには、画面全面に単色の色面が表示され、プログラムにより、その表情を変えてゆくのです。静かに建物の前に立ちはだかる色の壁は、来館者に強い印象を与えるものでした。
建物の中では、ロビーに大きなモニターが一台設置されていて、画面の中には日常の光景が、淡々とくり広げられています。窓越しの景色と同じそれは、よく観ると、どこか違っているように感じられるものでした。ここでは、鑑賞者と同じ場所からの眺めが、24時間遅れの映像としてモニターに映しだされていて、不思議な時間を経験することになります。この作品が、<内/外>。
階上では、グレイのフェルトが敷き詰められた500平方メートルほどの会場に、63台のスピーカーが配され、天井に整然と並ぶ光源から、すっくりと光が床に落とされた作品<内>。シックな色の床面には、ときに鮮やかな差し色が配されていて、会場に漂う気のアクセントになっていました。訪問者はここで、座ったり、寝ころんだりしながら、「音のある光景」の中にいつしか取り込まれています。
これら三つの作品で構成されたクーンの表現世界は、何かを境に生まれる、内側と外側という、きわめてシンプルな状況をいろいろなアプローチで鑑賞者に見せることに成功していました。
凍れる松明
2005年は、デンマークが誇るハンス・クリスチャン・アンデルセンの生誕200年目の年でした。この記念の年に、デンマークは国を挙げて、文化交流に取り組みました。とりわけ生まれ故郷のオーデンセは賑わいました。そして、この記念年のために、クーンは個展の開催だけでなく、市役所近くの公園において、野外のインスタレーション<Det frosne fakkeltong(凍れる松明)>を設置するチャンスを得たのです。クーンが題材にしたのは、かつて故郷に凱旋したアンデルセンを迎えたオーデンセ市民たちが松明を掲げ持って捧げた光の行列でした。
クーンは、公園の敷地内に200本の電灯を据え、そこに、吹き渡る風のように音を響かせました。それは、逍遙する人々に、これまでとはまったく違った公園の表情を見せました。師走の夜、青白い光は、凜として美しく冴え、凍てつき、時間が止まったようでした。そして、凍える空間を突き抜けて伝わってくるのは、抽象的な音。幻想的な音の世界でした。
それは、オーデンセの市民たちにとり、親しみのある、歴史的な出来事に捧げられた作品でしたが、一時的に設置された記念碑のようでもありました。
建築空間と関わる
ドイツの北西部、ニーダーザクセン州の州都、ハノーファーの西に、オスナブリュックという市があります。ここにあるフェリックス・ヌスバウム美術館は、ベルリン在住の建築家・ダニエル・リーベスキントが最初に手がけた、小規模ながら複雑なデザインが魅力的な美術館で、今や、建築に携わる人たちが世界中から訪れるようになりました。
ヌスバウムはオスナブリュック生まれのユダヤ人で、ベルギーに逃れていたものの、追放され、第二次世界大戦の終戦直前にアウシュビッツで殺害された画家です。遺された作品を常設するための美術館が建てられ、この不幸な絵描きに捧げられていたのですが、新しく建て替えられることとなり、ダニエル・リーベスキントがそのデザインを任されることになったのです。そして、新しい美術館のオープニングの展覧会に、リーベスキントはクーンを招くことにしたのです。
このとき、サウンド・インスタレーションの設置の場として、リーベスキントがデザインした複雑な空間を見渡し、クーンは、展示室の横に設けられた、狭く、長く、薄暗い通路<ヌスバウム・パッサージュ>と呼ばれる通路を選びました。息苦しくなるような、この空間のために、クーンは緊張感のある、張り詰めた作品を設置しました。それは、恐怖と絶望しかない人々が、アウシュヴィッツに向かう列車の暗闇の中で聞かされたであろう「音の光景」でした。訪れる人たちは、かすかに聞こえる音に鼓膜を刺激され、不安な気持ちをかき立てられます。ヌスバウムが隠れ家の薄暗がりの中で、息を潜めながら、どんな思いで筆を握っていたかを強く意識させる装置となっていました。建築家の空間デザインの意図を、クーンは見事に汲み上げ、美しいインスタレーションをもって、リーベスキントの招きに応えたのです。この作品は、クーンにはめずらしく、具体的なイメージを抱かせるもので、その多彩さと力量を見事に示しています。
当初、この作品は、開館記念展の後に撤去されることになっていました。しかし、クーンの作品を前にしたリーベスキントは、美術館に、この作品を恒久的に設置するように求め、美術館側もこれに応じたと言います。重く、苦しく、美しい、貴重な作品です。
フローズン・ヒート
立冬を過ぎ、本格的な寒さに襲われた頃、ウィーンやトリノなど、ヨーロッパを飛び回っていた作家から、今回の展覧会のためのタイトルが舞い込んできました。
<Frozen Heat>
「凍れる熱」というような意で、少しくだけた感じで表現するなら、「ヒートアップした状態を、瞬時にフリーズしてみせる」というようなことです。この感覚はとてもドイツ的だと感じられました。正反対の性質を持つものを突き合わせるところから生まれる強烈なイメージは刺激的で、この方法を用いる作家は少なくありません。しかし、この場合のあり余るエネルギーは、持てあまされがちでもあります。この方法をうまく扱うと感じさせる作家がドイツに多いことを、私はこれまでの経験から感じていました。クーンの作品にも、このことを感じていました。そして、何よりもこのタイトルが、穏やかで美しい瞳をしたこの作家の、知性溢れる外見の中にある、きわめてドイツ的な粘りや、温かい誠実さを連想させました。クールでシャープなコンセプトの中に在る、燃えさかる炎のような創作へのエネルギーにも繋がってゆきました。つまりこのタイトルは、作家の制作の姿勢そのものをも、よく表していると思われたのです。
クーンの創りあげる空間は、それほど多くの要素で満ちあふれているわけではありません。むしろ、かなりストイックに厳選されたものによって成り立つ場合が多いのです。おそらく、音楽のもつ多弁で、暴力的でさえある側面をよく知っているのでしょう。思えば、クーンの扱う音も光も、量の多寡にかかわらず、とても傍若無人で、自己主張の強い性質を持つ素材です。
今回の展示空間でも、私たちは空間がもたらすさまざまな表情とその刺激に出くわします。明るさや暗さ、狭さや広さ、騒がしさや静けさ、収斂や拡散の気配、など、少ない要素から、多くの表情を見いだすでしょう。それらがめまぐるしく取り込まれ、多彩な仕掛けにあふれた空間とそこを流れる静かな時間に、私たちはさらされ、向き合います。
クーンは言います。たいていの自分の作品の中には、「動き」と「静止」という二つの要素が存在するのだ、と。平易で静かに見えている光景の中に、どんなに複雑な要素が存在し、大きなエネルギーが内包されているのかを体験することで、新しい表現のあり方が見えてくることでしょう。訪れてくださる方の内側に、何らかの目覚めのあることを期して・・・。
特集:内なる目覚め
徳島県立近代美術館ニュース60号所収(2007年1月)
吉原美惠子 主任学芸員(展覧会担当)

 「シーニック・アイ 美術と劇場」展カタログも発売中です。
「シーニック・アイ 美術と劇場」展カタログも発売中です。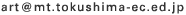 | ©2007 The Tokushima Modern Art Museum
| ©2007 The Tokushima Modern Art Museum