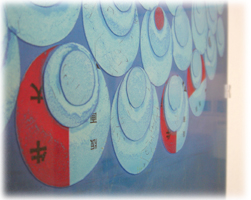
プレビュー:
木版画にかけた熱き日々-星と光のドラマ
竹内利夫
※写真は本展のために貸し出された〈眼球体〉原版。作家蔵。
「木版画って、こんなに色鮮やかなんですね。」2006年4月、世田谷美術館オープニングの内覧会で、鑑賞されている方の声を耳にしました。木版画と言えば、墨一色の簡素な絵柄をイメージする人も多いのではないかと思います。私もそうです。この展覧会をご覧になって、版画に対する考えや、一人の画家がどんなに表現の世界を旅するものかということについて、新しい発見をしていただけたならと願っています。では、ご案内しましょう。
ビッグバン創世
展覧会の冒頭を飾るのは、宇宙に浮かぶ惑星や星々を思わせるダイナミックな吹田ワールドです。色とりどりの光線がゆきかう画面は鮮烈で、確かに従来の木版画の発想を超えた迫力を感じさせます。〈白鳥座〉はその中の1点。黒い宙空に青や緑の澄んだ光がたちのぼり、白い花びらがもくもくと重なり合って開いています。吹田文明さんの描く世界は、抽象的なように見えて、自然や宇宙への自由な連想を誘いかけます。画家としての円熟期を迎える1970年代から一気に展開した、これら宇宙のシリーズには、木版画の可能性を探り続けてきた歩みが凝縮されています。作家は一貫して、抽象的な造形に詩情を求めながら、自らを一番表現できるテーマとして宇宙にたどりついたのでした。「絵は透明な空間によって作り出される永遠でなくてはならない。それは宇宙の果てしない空間であり、星の透明な輝きである。」*1
リズミカルに、まるで生命体のように星々が浮遊する空間は、重厚な色彩と透明な光の巧みなコントラストから生まれています。その秘密は、油性と水性のインクを駆使したり、紙や木片による版を自在に取り入れたりする、吹田文明さん独特のテクニックにあります。それは若い時代から、作家が一つ一つ試行錯誤を重ねた成果に他なりません。自分が描きたい絵を求めて、オリジナルな方法を模索し続けてきた様子が、半世紀におよぶ制作の変遷から理解していただけると思います。
図工科教材研究からの出発
1926(大正15)年、徳島県阿南市に生まれた吹田文明さんは、はじめ小学校の教師として、戦後の図工科教育の研究で先駆的な活動を繰り広げました。子どもたちが楽しんで版画に取り組めるよう、紙の版を使ったり、身近なものを版にしたりする教材研究は、今日まで新鮮さを失っていません。その発想の柔らかさが、当時、油彩画と版画の両方を描いていた自身の制作にも活かされているところに、作家吹田文明の出発点がありました。ひもや板切れを使った〈民話〉はその頃の1点です。初期の作家はこのように、純粋に抽象的な構成の中へ日本風の詩情を込めていたようです。会場には、実に様々な方法を試みた若き日の実験作が並びます。
機械と人間
1950年代後半、版画教育の成果が高い評価を受ける一方で、彼は徐々に作家としても頭角をあらわしていきます。モダンアート協会、日本版画協会、あるいは若手同士のグループ展などで活躍する中で、1958(昭和33)年には、第1回グレンへン国際色彩版画トリエンナーレで受賞を果たしました。そこで生まれたのが「眼球体」のシリーズです。教材研究を通して見出した紙版の表情を活かし、群生する目玉を描いたこの時期のテーマとは、工業化社会・高度経済成長の時代へ突き進もうとする時代の人間の姿でした。大衆の寓話を思わせるメッセージ性に関心を集中したことで、吹田版画は初期の模索的な造形から明解な飛躍をとげました。この時期の作品に〈機械と群衆の中より逃れる〉があります。古い額縁をひっくり返すと、「博物館様/昭和三九年六月/徳島にて個展にて」と大きく墨書きされています。この年に故郷での初個展を県立博物館で開いた折りに寄贈された作品です(現在は当館蔵)。徳島を離れ東京を拠点とした作家でしたが、実にこまめに徳島新聞の紙面へ近況を寄せたり、個展を開いたりされています。この度の展覧会準備のためにお預かりしたスクラップ帳には、そんななつかしい記録もぎっしりと綴じられていました。
ラワン・メゾチント法
小学校の運動会などの行事で使われるラワンベニヤ板を版木としたことで、新たな表現の幕開けを作家は迎えます。細密な彫りには向かない、ラワンベニヤ板の目の粗さを逆手にとって、縦横互い違いに木目を重ねた効果を活かし、ちょうど銅版画のメゾチントにも似た技法が考案されました。互い違いと言うと単純に聞こえますが、聞くと見るとでは大違い。実際の作品は幾重にも交差した複雑な織物のように、実に面白い奥行きと風合いを感じさせます。そこに色彩の効果が加われば、まさに表現の幅は無限に広がるのです。子どもたちが扱いやすい油性インクの開発と、みんなで大きな合作を刷るための木版プレス機の開発に、作家は取り組みました。それらの版画材科は、ラワン・メゾチント法の確立にとっても欠かせないものでした。展覧会では、この新しい技法によって黒一色の画面から再出発し、赤、青、と一色ずつ深みをつかんでいく熱中ぶりをていねいに紹介しました。新しい技法の発見に掛けた意気込みを感じるのは決して私だけではないだろうと思います。作家としての自覚を心強くした、気迫のようなものを作品群は伝えてきます。
また「制作の現場から」のコーナーでは、代表作の版木をお借りして展示しています。どうぞそばでご覧になって、どうやって作品が刷られているか目で追ってみて下さい。これが意外と難しい。だから作っていても楽しいのかなと思った次第です。
サンパウロ・ビエンナーレ受賞
棟方志功、浜口陽三に続いて、版画部門最優秀賞3人目の快挙となった、1967(昭和42)年のサンパウロ・ビエンナーレ受賞は、作家の人生に大きな衝撃を与えました。小学校教師としての教育現場への複雑な思いを抱えながら、吹田文明さんは現代版画のリーダー的存在として制作活動にはげむ道を選びます。受賞作の1点〈野の2人〉は、一目見れば忘れられないような、光点の集中と分散が特徴的な、作家の代表作です。メゾチント的な闇と色彩の効果を探求してきた制作に風穴を開けたのは、またしても従来の木版画の考えでは発想できないような、ドリルの活用でした。重ねた版材を一気に貫通する光の点は、星となり花火の閃光となり、抽象的でありながら人をひきつけて止まない明快な作風がここに完成します。
青と赤の2人とは野に遊ぶ男女の姿でしょうか。いいえ、ミクロの世界の植物の営みのようにも見えます。作家は、「総ての物質は点と円の集積によって作られていると考えている」と語っています。*2 初期の目玉シリーズを想起させはしないでしょうか。人間社会をみつめてきた作家の思想と方法論が、この光点の表現において実を結んだと言えるのでしよう。
新旧織り交ぜ実力伯仲の20名の日本作家の中から、受賞を射止めた吹田文明さんを、海外の記者たちは「花火の男」と呼んだと言います。伝統的な木版画の世界を斬新に塗り替え、けれど嫌みのない明朗さに昇華させた吹田版画は、確かな説得力をもってストレートな人気を獲得したのでした。
光の彼方へ
受賞を機に大学へ拠点を移した作家は、駒井哲郎らと育てた大学版画学会を主導し、多摩美術大学に日本初の版画科を創設するなど、ここでも改めて版画教育の活性化と、自己の絵画世界の深化に力を注ぎます。精力的に作風を展開した1970年代以降の作品については、冒頭でお話したところです。さて、近年の作家は、一つの特徴的な変化を経験してきたように思われます。展覧会のフィナーレを飾る「光の彼方へ」のコーナーでは、近作で取り組まれてきた荘厳な光の世界と、作家のまた別の一面をのぞかせる、大地や大海原を思わせるような心象風景とも言える作品群を合わせて構成します。
1995(平成7)年、戦後50年を期して手掛けられた「鎮魂」のシリーズは、華やかな色彩空間がより洗練度を増しながら、どこか内省的な深みへと見る者を導いていくかのようです。静かに浮遊する形には、あてどない心情や静謐な激しさすら感じられるように思います。そして、近作の〈悲しみのニケ〉といった作品が持つムードは、作家がはっきりと感情をテーマに制作していることを私たちに伝えてきます。かつて作家は、純粋な造形空間を求めて抽象的な表現から出発し、自らの絵と出会うためにこそ、木版画のフロンティアを駆けてきました。より内面深くに醸成されてきた作家の思想と表現は、さらなる光を求め、新たな展開へ向かっているようにも思われます。
〈友よ永遠に飛べ(戦後50年の鎮魂詩)Ⅵ〉の赤く焼けつくような光は、はかなく群れをなす蝶たちに襲いかからんとするようにも、遠い場所へと導いているようにも見えます。その明るい光の影にあるものを見ることもなかった私は、「無くした戦友を思い出して苦しい」と語る人がおられるという逸話を聞いて、自分の絵を見る力のなさに言葉を失う思いでした。
「一時、版画がようやく分かったなと思えた時期があった。はなけど、やっぱりまた分からなくなっている。だからまだ作り続けるんだと思う。」アトリエでそう語る吹田文明さんの言葉を聞いて私は、半世紀にわたる制作歴の重みといったものもさることながら、むしろ何か清々しいピュアなバイタリティに感じいったことでした。一人の画家が過ごしてきた長い時間をたどって歩きながら、私たちもまた、迷いながら発見しながら絵のこと版画のことをあれこれと考えることができたなら、そういうことが展覧会の一番大切なことではないかと考えています。
(徳島県立近代美術館 主任学芸員)
*1 「朝日新聞日曜版」1979年6月17日より
*2 『版画藝術』21号(1978年春)より