
60年代以降 アーティスツ・ブックスの時代 1960年代以降になると、本という形式やあり方、メディアとしての特性に立脚して芸術家が制作する本、いわゆるアーティスツ・ブックスが出現します。 アメリカのアーティスト、エドワード・ルシャの<26のガソリンスタンド>(1963年初版)は、アーティスツ・ブックスの原点の一つであると言われています。この本では、自宅のあるロサンゼルスからルシャの故郷オクラホマまでの道「ルート40」沿いにあるガソリンスタンドの写真が延々と26枚続くだけです。説明もなにもありません。簡素な作りで値段も安く(当時で約3ドル)、大量生産も可能。これまでのプレミアがつくような豪華な挿絵本とは大違いです。これは、、美術作品が高価で貴重なものだという思いこみに対する反発であり、アートの大衆化でした。それは同時期のポップ・アートなどの方向性とも重なっています。 ● ● ● 日本でも本を表現の手段とする新しい作品が盛んに作られました。前面と上下左右にガラスの入った箱に、大岡信の未発表詩集と様々なオブジェが収めた加納光於の<アララットの船あるいは空の蜜>(1971-72年刊)。吉増剛造の詩を鉄のケースに収めた若林奮の<LIVRE OBJET II>(1971年刊)。稲垣足穂の短編を全て銅で仕立てた中村宏の<稲垣足穂『イカルス』>(1973年刊)。これらの作品は、実は本というものは間違いなく物質なのである、ということをまざまざと感じさせてくれます。本はオブジェとなったのです。 山口勝弘の<リベール リベール>(1975年)は鏡の箱です。 概念的な作品や、物質性にこだわった作品、記録としての意味を追求した作品など、多様な成果が生んできたアーティスツ・ブックス。それは、これまでの「本」を解体した後、どのような可能性を見せてくれるのでしょうか。
図版: 山口勝弘<リベール リベール> |
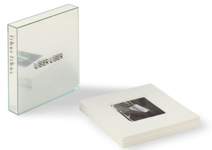 そこには言葉も挿絵もページすらありません。鏡は時々刻々と変化するまわりのものを映すだけです。テレビに象徴されるように、時代はしだいに、文字を中心とした情報から、映像を中心とした情報に移り変わってきました。さらに、インターネットの時代になると、情報は、整理され記述されたものから、それ以前の生の状態で直接発信し検索されるものに変わってきています。鏡に映るものも生の情報です。そこに映っている人や情景は、知らないうちに、自らが本の登場人物となっているのです。この作品は、情報伝達を象徴してきた本のあり方を考えながら、情報や伝達の行く末を暗示しています。
そこには言葉も挿絵もページすらありません。鏡は時々刻々と変化するまわりのものを映すだけです。テレビに象徴されるように、時代はしだいに、文字を中心とした情報から、映像を中心とした情報に移り変わってきました。さらに、インターネットの時代になると、情報は、整理され記述されたものから、それ以前の生の状態で直接発信し検索されるものに変わってきています。鏡に映るものも生の情報です。そこに映っている人や情景は、知らないうちに、自らが本の登場人物となっているのです。この作品は、情報伝達を象徴してきた本のあり方を考えながら、情報や伝達の行く末を暗示しています。